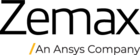Zemaxソフトウェアを活用した、超小型人工衛星CubeSatの光学系の仮想試作ワークフローをご紹介します。こちらのコミュニティフォーラムにて、事前の質問および開催後の質問を受け付けております。お気軽にコメントを投稿ください。
日時:2022 年 4 月 13 日(水)14:00-15:00
参加リンク:オンラインセミナー登録ページ
アブストラクト
AnsysとZemaxのソフトウェアの高度な連携により、超小型衛星の規格CubeSat (キューブサット)の設計ワークフローを合理化する事例を紹介します。OpticStudioが光学設計、OpticsBuilderがオプトメカ設計、有限要素解析ソルバーのAnsys Mechanical が構造熱解析、STARモジュールがOpticStudioでのSTOP分析を行います。この設計・解析プロセスを短時間で回すことで反復検証の試行数が増加し、信頼性の高い製品を実現する仮想試作が実現できます。
プレゼンタ:Zemax Japan 株式会社 シニアアプリケーションエンジニア 石川 孝史 (